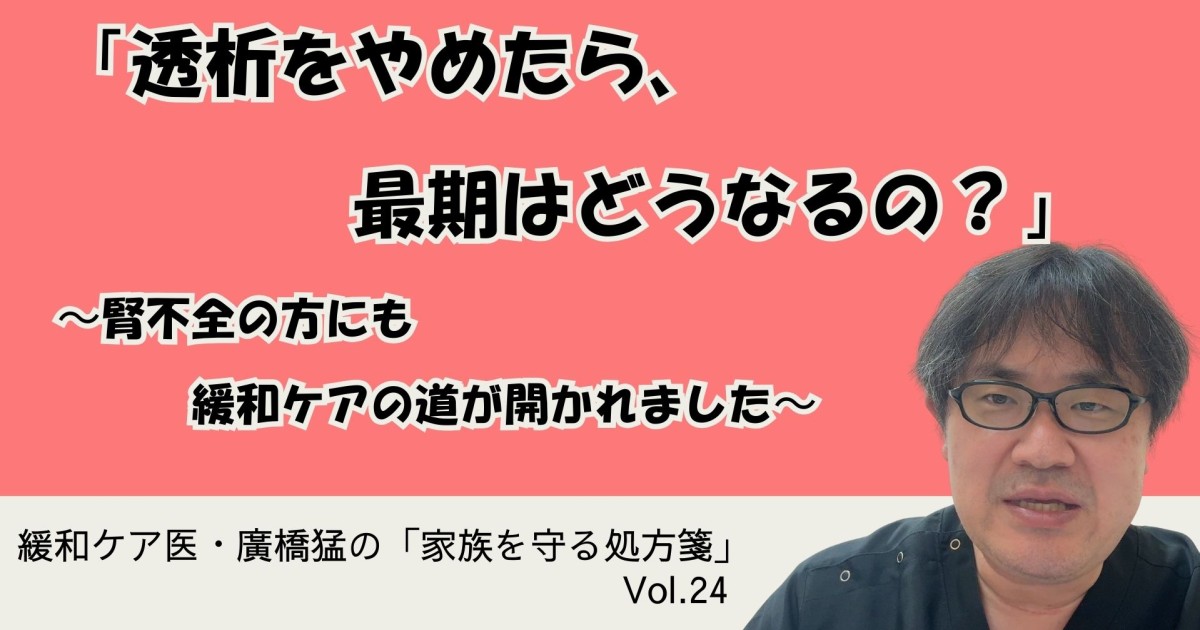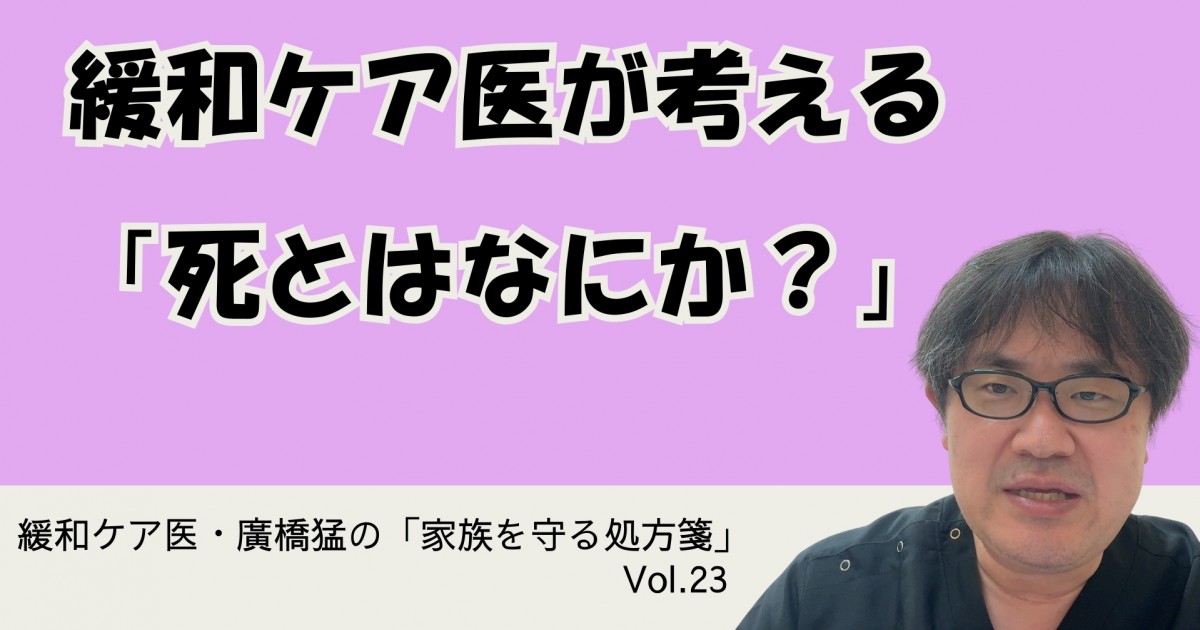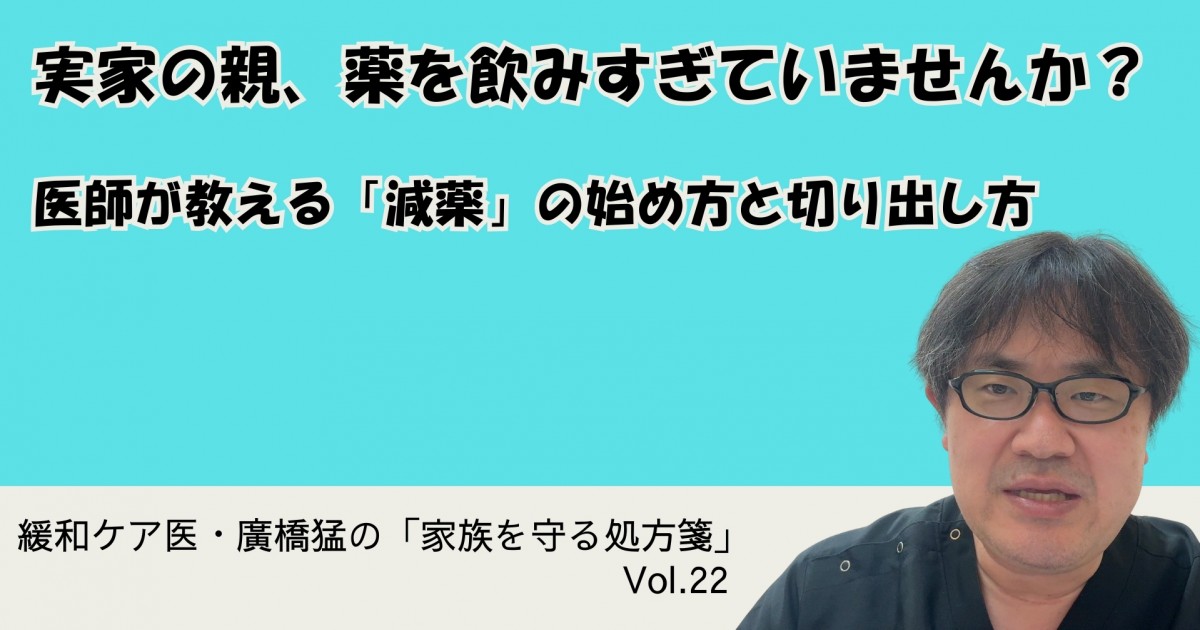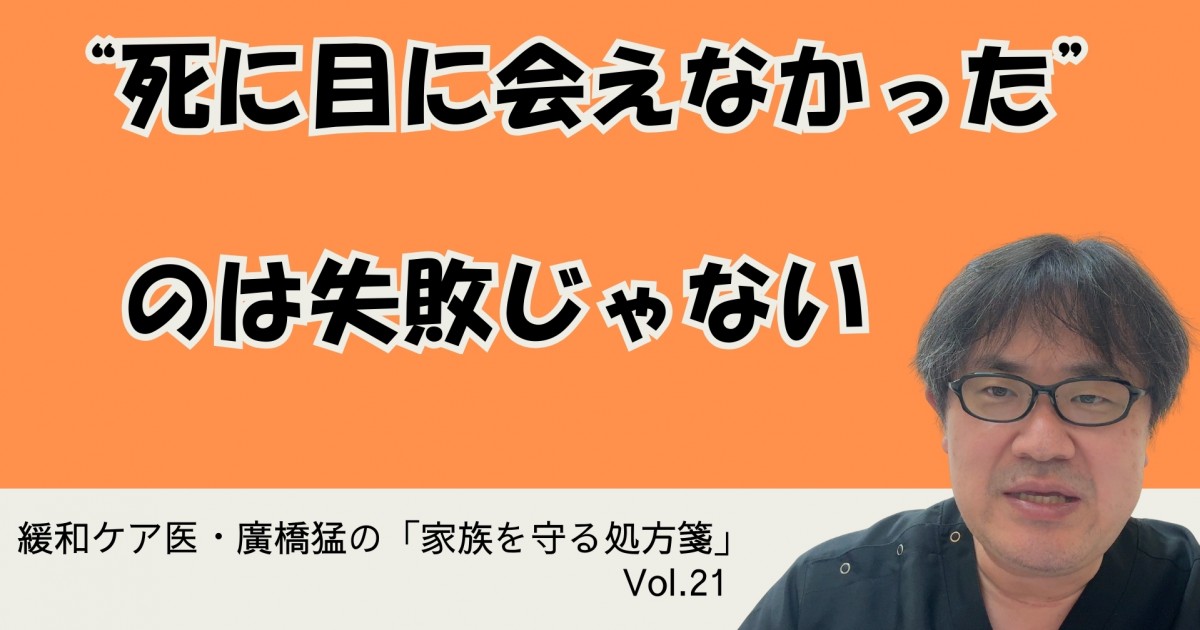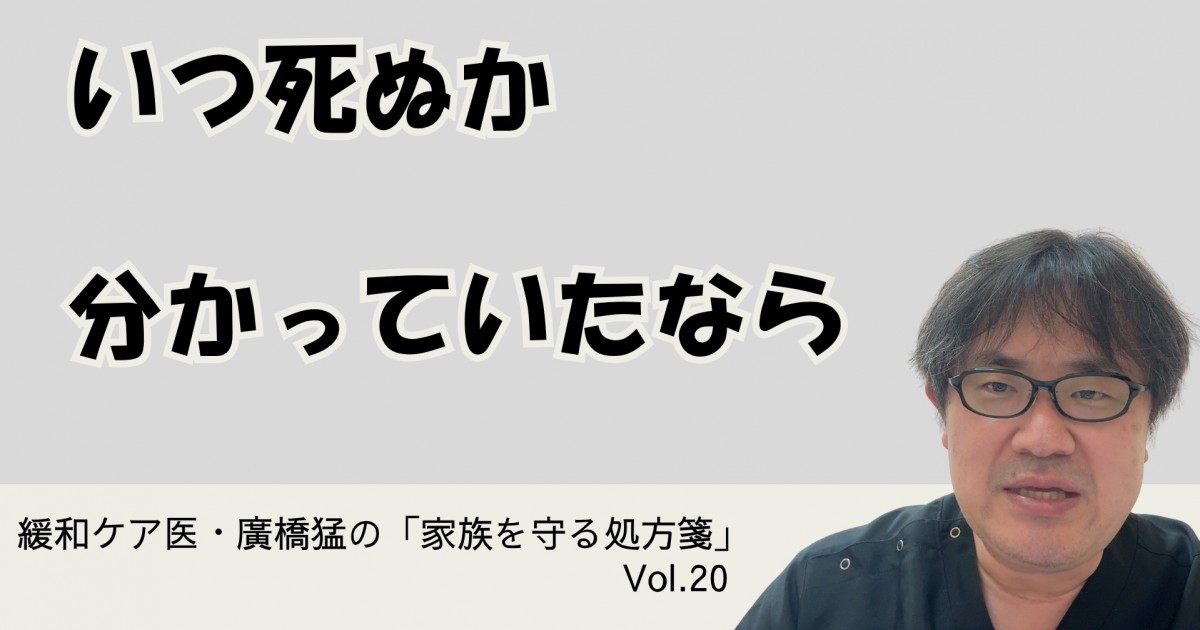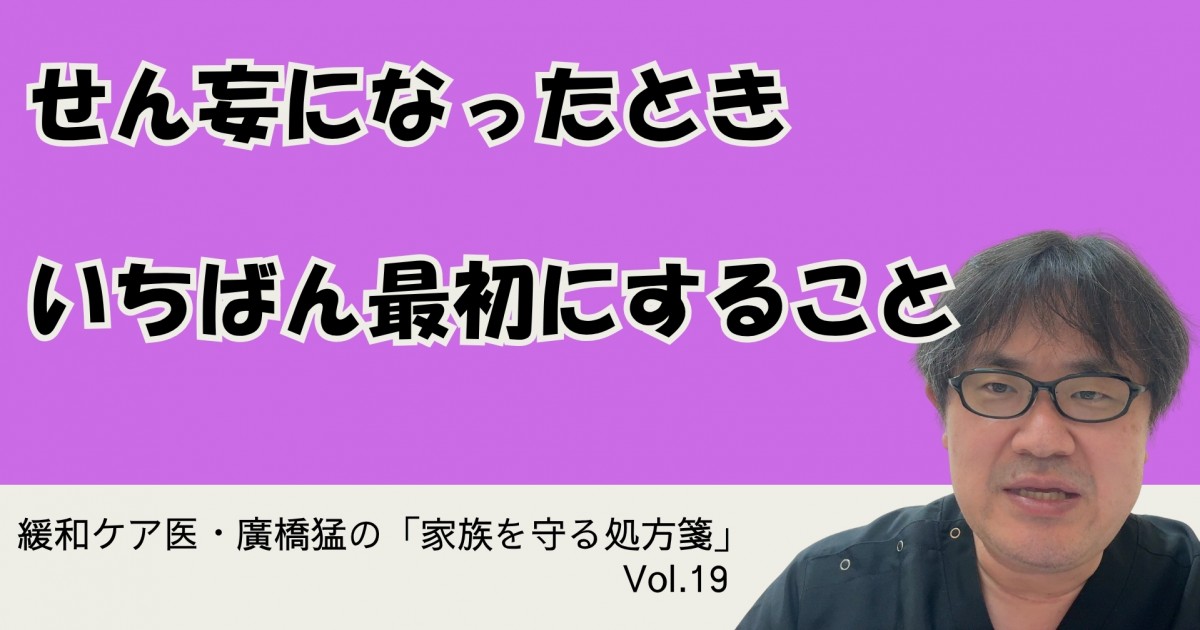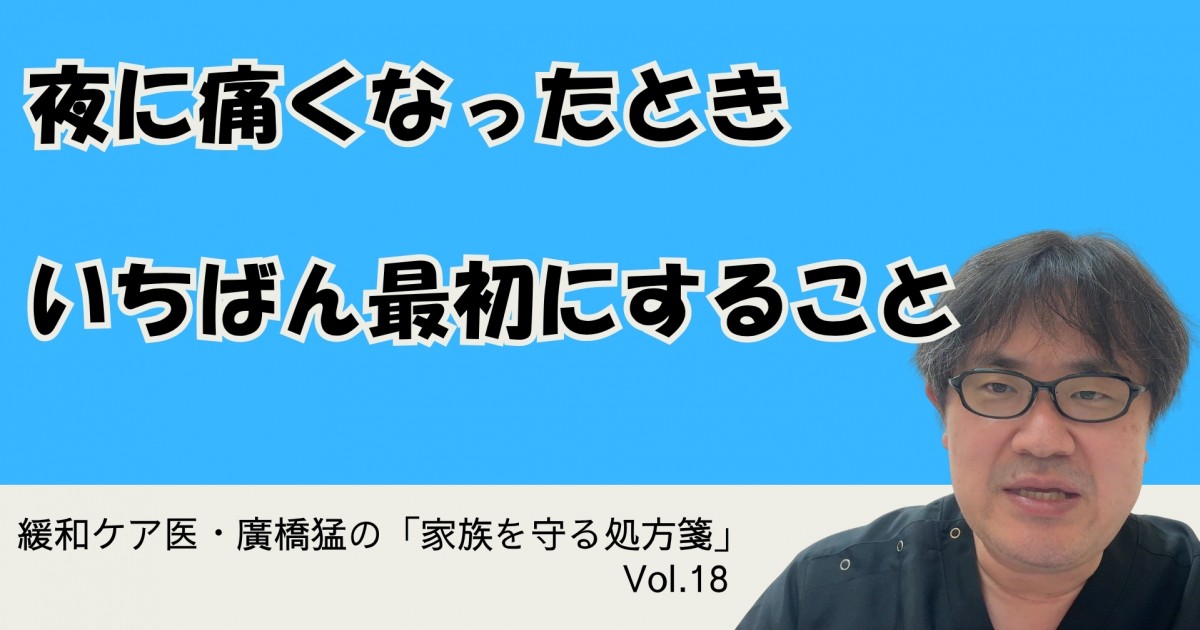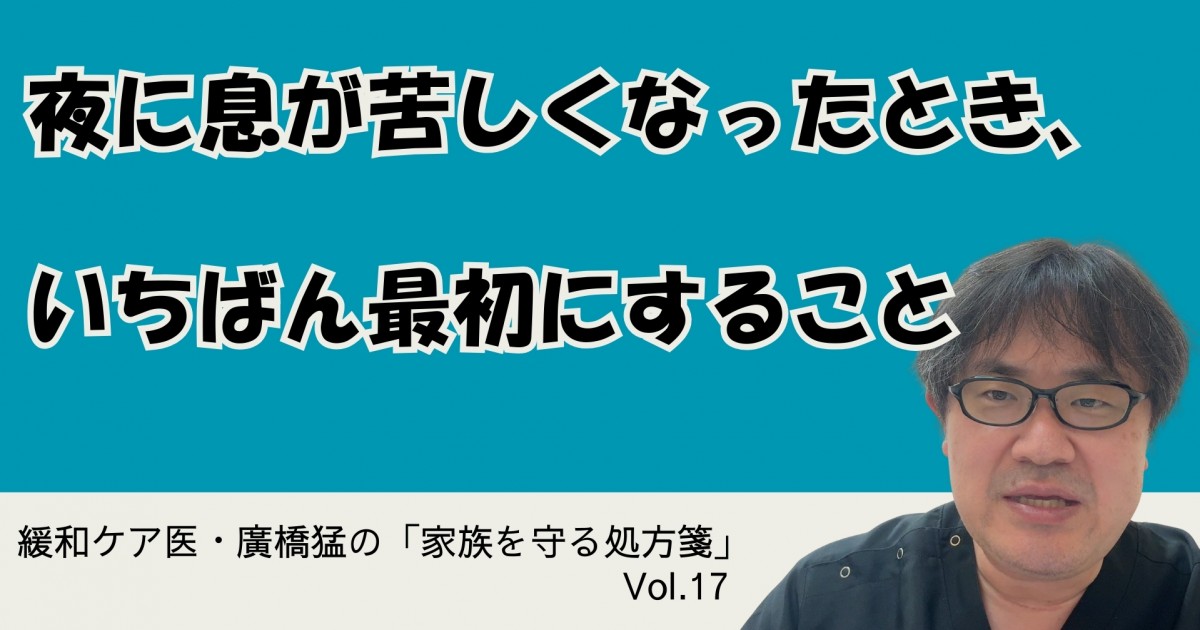人生最期の一口はガリガリ君? ~栄養よりも大切な「味わう」ということ~
皆さん、こんにちは。緩和ケア医の廣橋猛です。
緩和ケア医・廣橋猛の「家族を守る処方箋」をお読みいただき、ありがとうございます。
はじめに
前回のレターでは、人生の最期が近づいたときに、身体にどのような変化が現れるかについてお話しました。その中で、「だんだんと食事や水分を摂らなくなる」という変化は、そばで見守るご家族にとって、とても寂しく、そして心配なことの一つだと触れました。「何も食べられなくなったら、どんどん弱ってしまうのではないか」「何か少しでも口にしてほしい」…大切な人を想えばこそ、そう願うのはごく自然な、温かい気持ちだと思います。
しかし、私が緩和ケアの現場で多くの患者さんとご家族に接する中で、常々感じていることがあります。それは、「食べられなくなった」からといって、口にする喜びや、そこから生まれる繋がりが完全に失われるわけではない、ということです。いえ、むしろ人生の最終段階においては、「食べること」の意味合いが、「栄養を摂る」ことから、「味わう喜び」「心地よさ」「家族と共有する時間」へと、自然に、そして豊かにシフトしていくのかもしれない、と感じています。
今回の処方箋では、この「人生最期の一口」という、少しデリケートだけれど、とても大切なテーマについて、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。栄養を摂ることよりも、その一口がもたらす「味わう」という経験が、ご本人とご家族にとって、どれほど温かく、意味のある時間となりうるか、私の経験も交えながら、具体的なヒントをお伝えできれば幸いです。
第1部:なぜ「食べる」から「味わう」へ?終末期の食とその意味
身体が求める「休息」:なぜ食べられなくなるのか
まず、大切なこととして、終末期に食欲が自然と落ち、食べる量が減っていくのは、多くの場合、身体が穏やかな休息へと向かうための自然なプロセスの一部だということを、ご理解いただければと思います。
人生の最期が近づくと、身体全体の活動はゆっくりとなり、たくさんのエネルギーや水分を必要としなくなります。心臓や肺、消化管などの臓器の働きも穏やかになり、消化・吸収する力も自然と低下していきます。これは決して「病気に負けてしまった」とか「生きる気力を失った」という単純な理由だけではなく、身体が次の段階へと静かに、そして自発的に準備を始めているサインなのです。
ですから、この時期に「栄養をつけなければ」という思いから、ご本人にとって負担になるほど食事を勧めたり、あるいはたくさんの点滴をしたりすることは、必ずしもご本人のためになるとは限りません。むしろ、消化できない食べ物がお腹の不快感につながったり、過剰な水分や栄養が体のむくみや胸腹水、痰の増加を招き、苦しさなどの苦痛を増やしてしまったりすることさえあるのです。
「食」が持つ、栄養を超えたチカラ:「思い出の味」が呼び覚ますもの
では、食べる量が減ったら、もう「食」に関する喜びや意味はなくなってしまうのでしょうか? 私は全くそうは思いません。なぜなら、私たち人間にとって「食べる」「飲む」という行為は、単に体を維持するための栄養補給という側面以上に、もっと豊かで深い意味を持っているからです。
少し思い出してみてください。家族みんなで囲んだ温かい食卓の光景、お祝いの日に食べた特別なケーキの甘さ、故郷のお祭りで友達と分け合った懐かしい味、旅行先で初めて口にした感動的な料理…。私たちの人生は、「食」にまつわる様々な記憶や感情、人との繋がり、文化、そして「生きる喜び」そのものと、強く結びついています。その食事の瞬間は、理屈抜きに私たちを幸せな気持ちにしてくれますよね。

そして、味覚や嗅覚というのは、たとえ体が弱ってきたとしても、比較的最後まで残りやすい感覚だと言われています。ほんの少しの味や香りが、ご本人の遠い記憶を鮮やかに呼び覚まし、心を穏やかにさせたり、ふっと安らかな笑顔がこぼれるきっかけになったりすることがあるのです。特に、ご本人が若い頃からずっと大好きだった「思い出の味」、例えばお母さんが作ってくれたお味噌汁の味や、特別な日にだけ食べたお菓子の味などは、一瞬でもその人らしさを取り戻させてくれるような、特別な力を持っているのかもしれません。
だからこそ、緩和ケアの現場では、「食べられなくなった」から終わり、ではなく、「味わう」「楽しむ」という、より本質的な経験に焦点を当てて、最期までその人らしい喜びや心地よさを支えられないか、と考えるのです。
第2部:「どうしても食べたい」に応える~ガリガリ君と最期の一口の工夫~
「食欲はないみたいだけど、時々『あれが食べたいなぁ』と呟くことがあるんです」「何か口にさせてあげたいけれど、何がいいか分からなくて…」そんなご家族の声もよくお聞きします。ここでは、「最期の一口」を叶えるための具体的な工夫と、その際に大切にしていただきたい心構えについてお話しします。