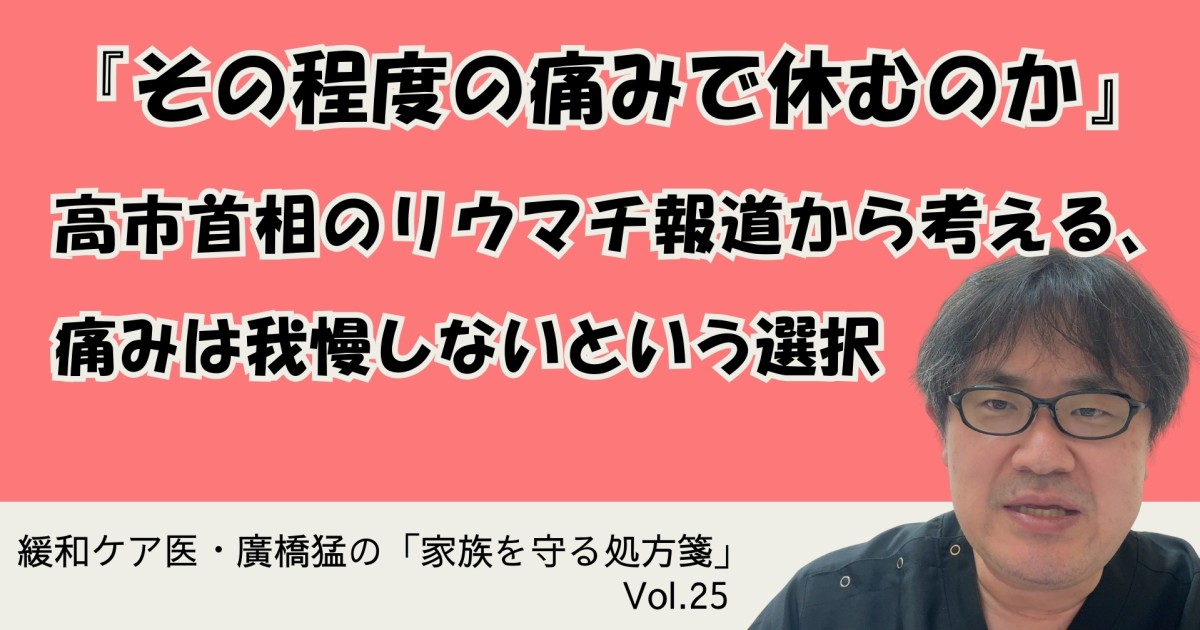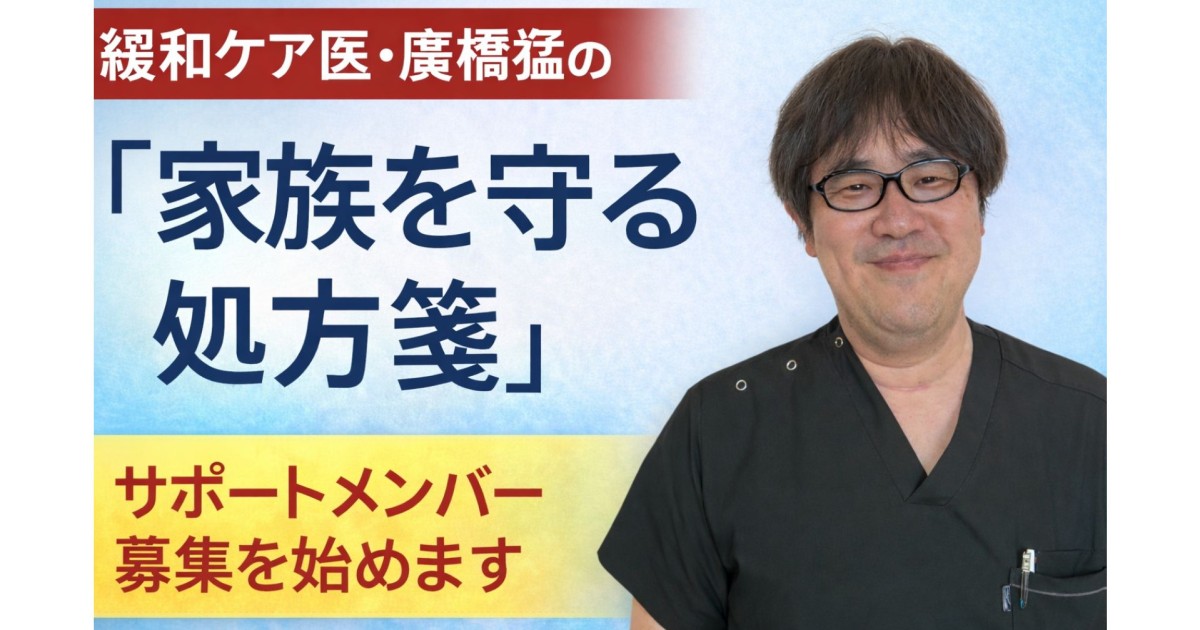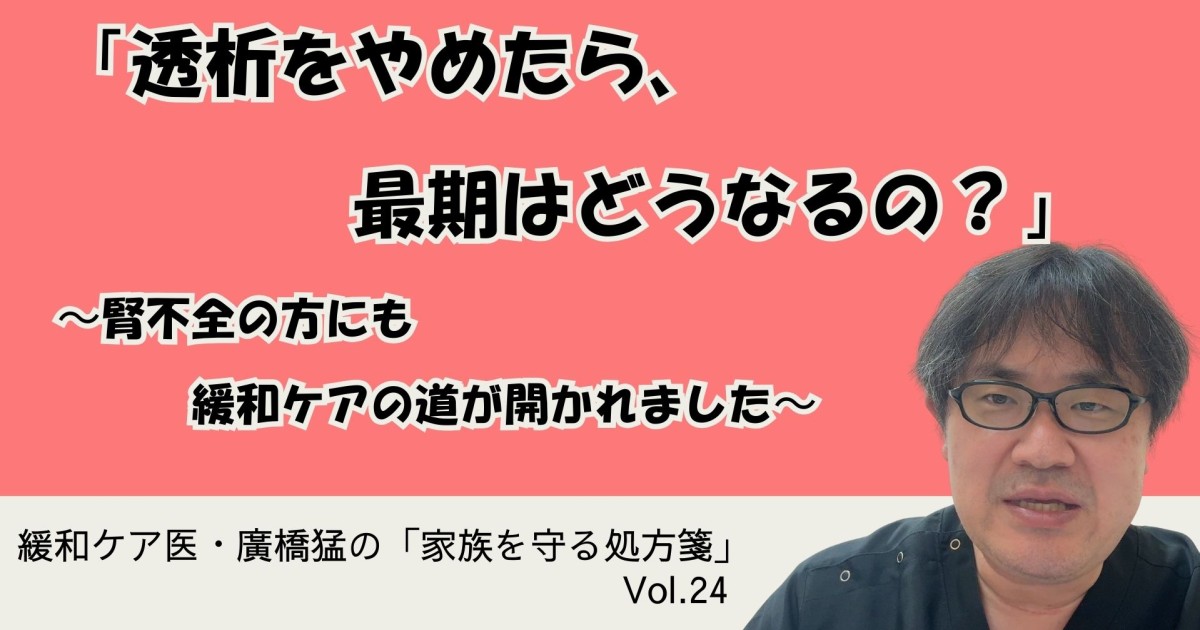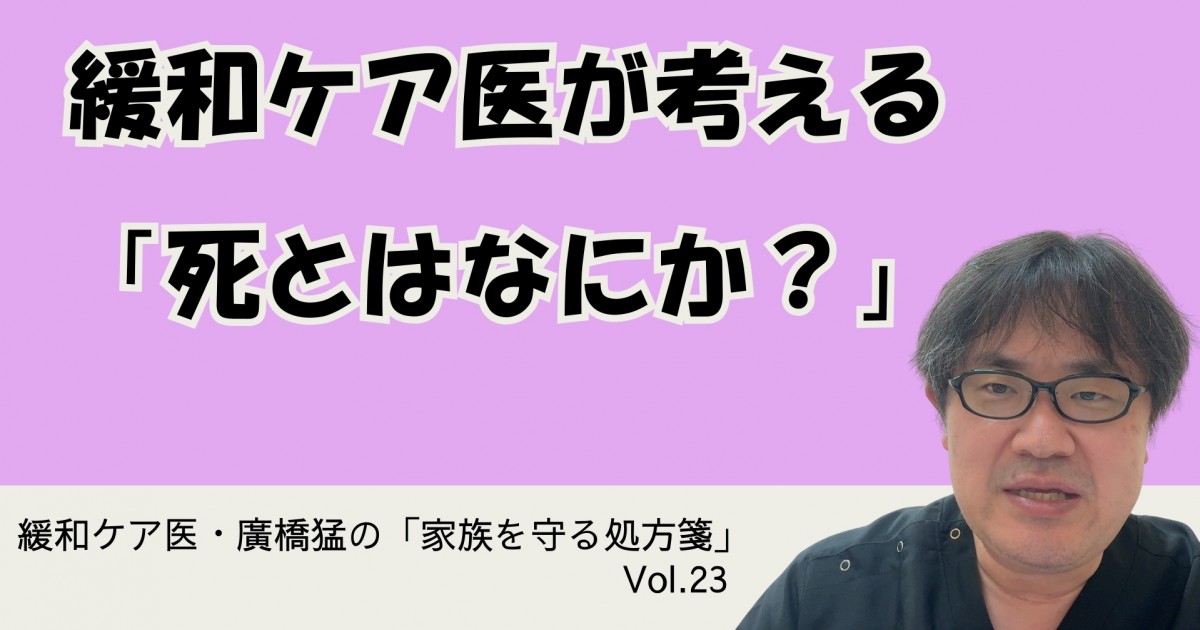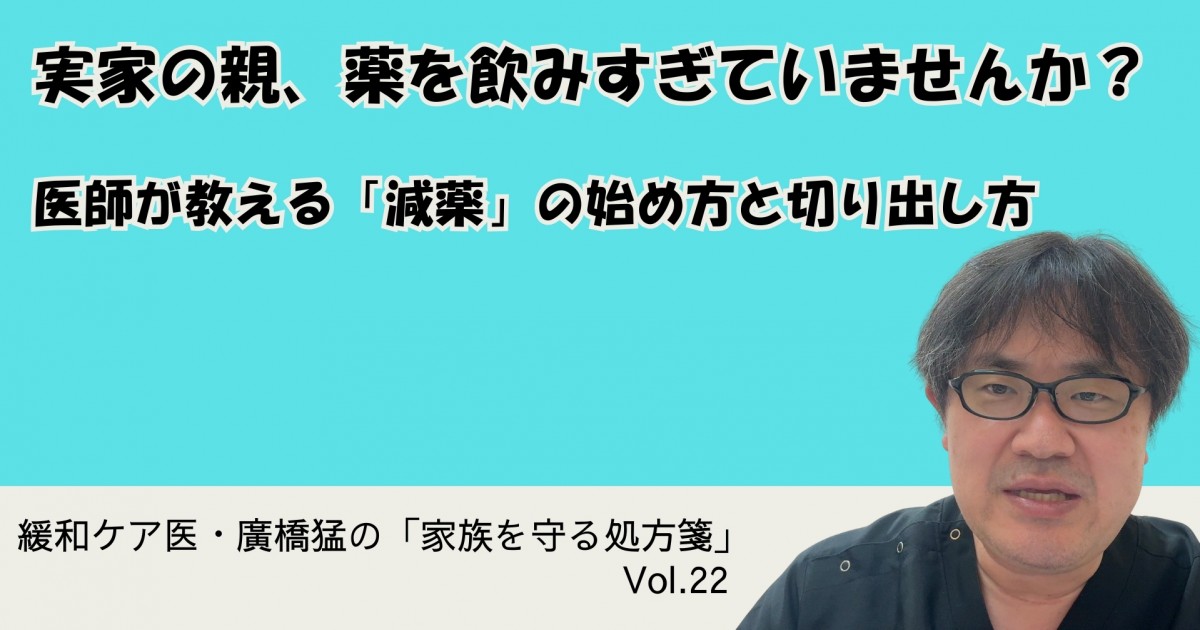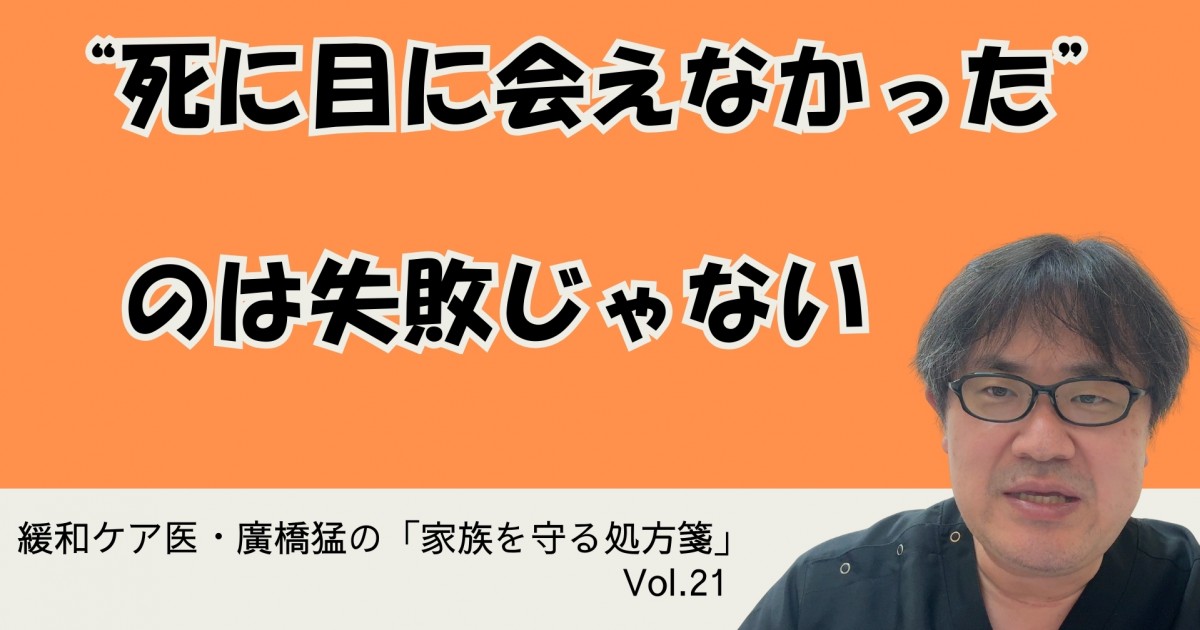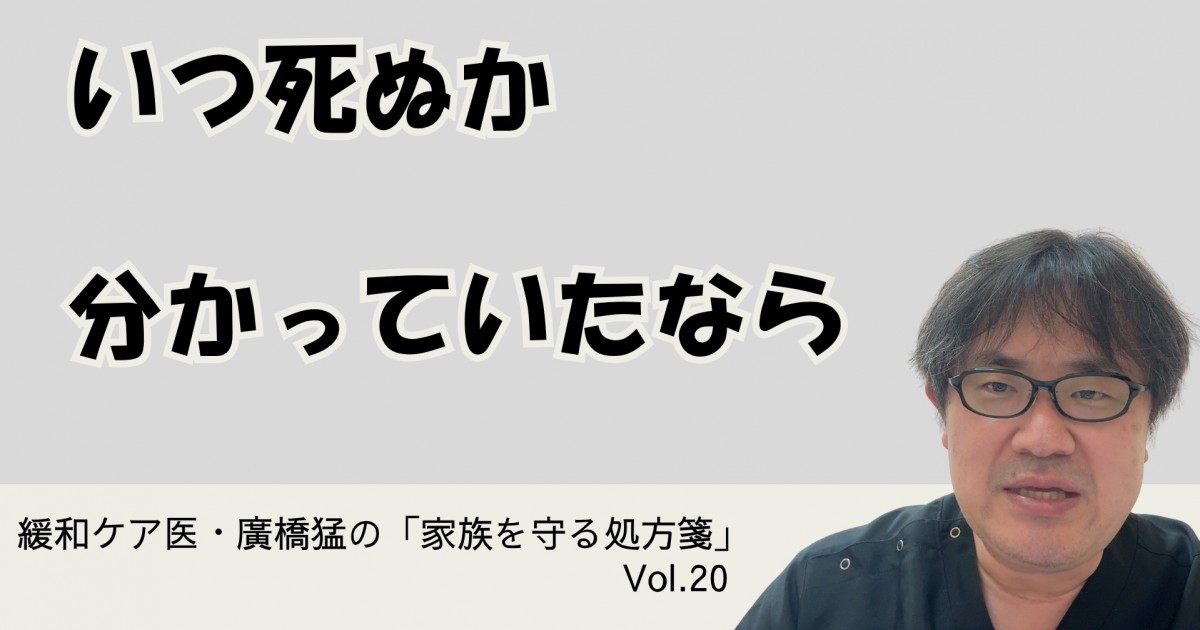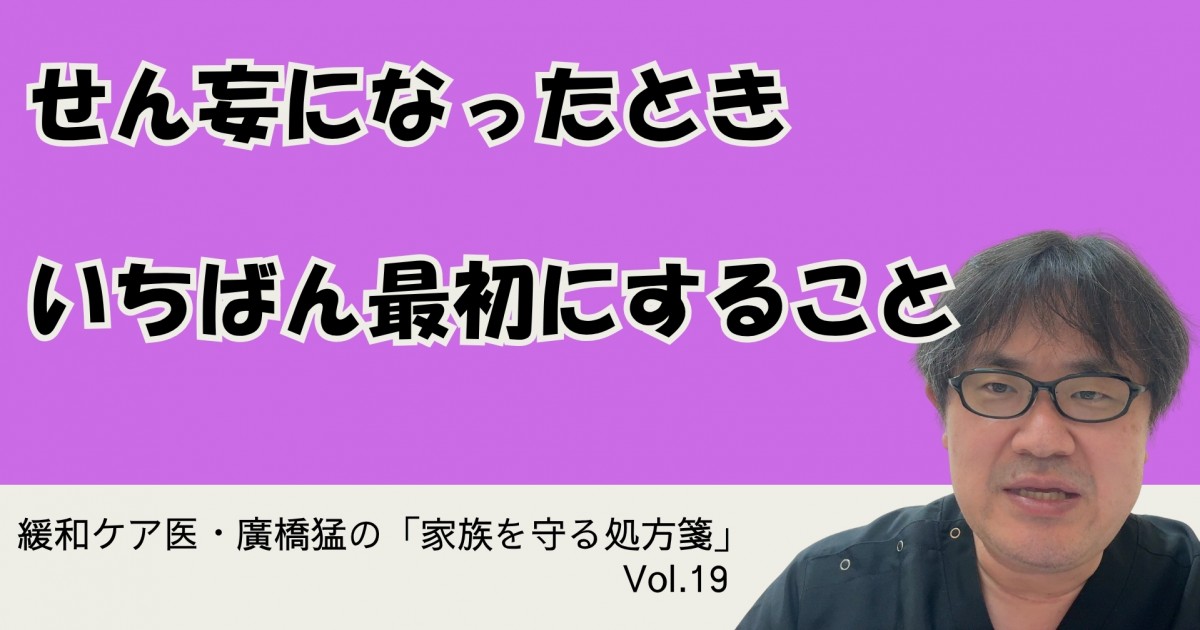「終末期って、いつから?」〜後悔しないための“時間”のとらえ方〜
皆さん、こんにちは。緩和ケア医の廣橋猛です。
いつも「家族を守る処方箋」をお読みいただき、ありがとうございます。
先日公開した「誤解だらけの終末期の食事と水分補給」の記事には、本当に多くの方から反響をいただきました。その中で、このようなご質問をいくつかいただきました。
「終末期の食事のことはよく分かりました。でも、そもそも『終末期』って、いつからを指すのでしょうか?」 「家族が終末期に入ったとき、私たちは分かるのでしょうか?」
確かに、そうですよね。「終末期」という言葉は、誰もが知っているようで、その実態は曖昧です。
死刑宣告のように響くこの厳しい言葉に、私たちはどうしても身構えてしまいます。
ある人にとっては「もう治療がない」という絶望の宣告に聞こえ、またある人にとっては「最期の準備を始める」という静かな合図に聞こえるかもしれません。

言葉の悪さから、最近では「人生の最終段階」という言葉に置き換えて用いられることもあります。でも分かりにくいので、本稿では割り切って「終末期」で通します。
この言葉の捉え方が、ご本人やご家族、そして私たち医療者の間ですれ違ってしまうと、時に大きな後悔を生むことがあります。
そこで今回は、この「終末期」という、誰もがいつかは直面する時間について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
終末期は、誰の、どの視点から見るかによって、その始まりのタイミングが少しずつ違って見えます。この「視点の違い」を知っておくことこそが、残された時間を大切に、そして穏やかに過ごすための最初の「処方箋」になるのです。
なお、長文を読む時間や余裕のない方は、一番最後にまとめとして私からの処方箋を掲載していますので、そちらだけご覧いただいても構いません。
1. 「終末期」は誰の言葉? 3つの異なる視点
「終末期」という言葉は、実は使う人の立場によって、少しずつ意味合いが異なります。
大きく分けると、①行政・保険、②医療者、そして③患者さん・ご家族の体感という3つの視点があります。
まずは、それぞれの立場が「いつから」をどう捉えているのか、下の表に沿って見ていきましょう。

①「行政・保険」の視点:サービスを受けるための「ものさし」
まず、行政や保険制度における「終末期」です。これは、介護保険で特定のサービスを受けたり、アメリカではホスピスケアの保険給付を開始したりするための、いわば「公的なものさし」としての定義です。多くの場合、「余命6か月以内と医師が判断」が一つの基準となっています。
これは、誰にどのようなサービスを提供するかを公平に決めるために必要な「線引き」です。少しドライに聞こえるかもしれませんが、この基準があるからこそ、私たちは必要な公的サポートを受けられるのです。