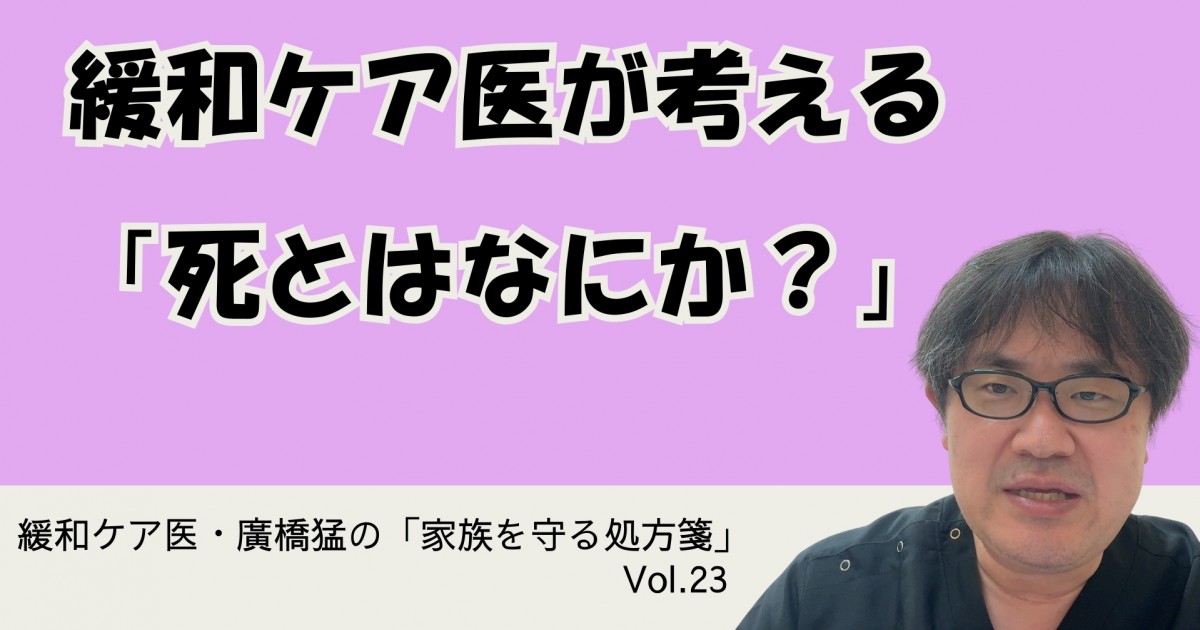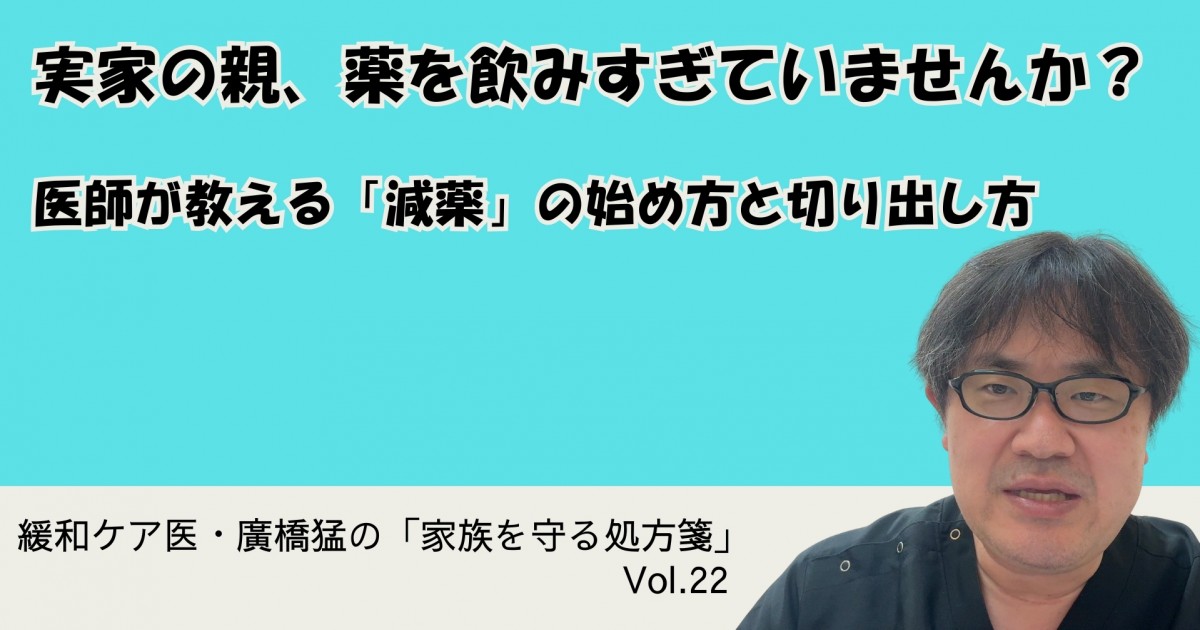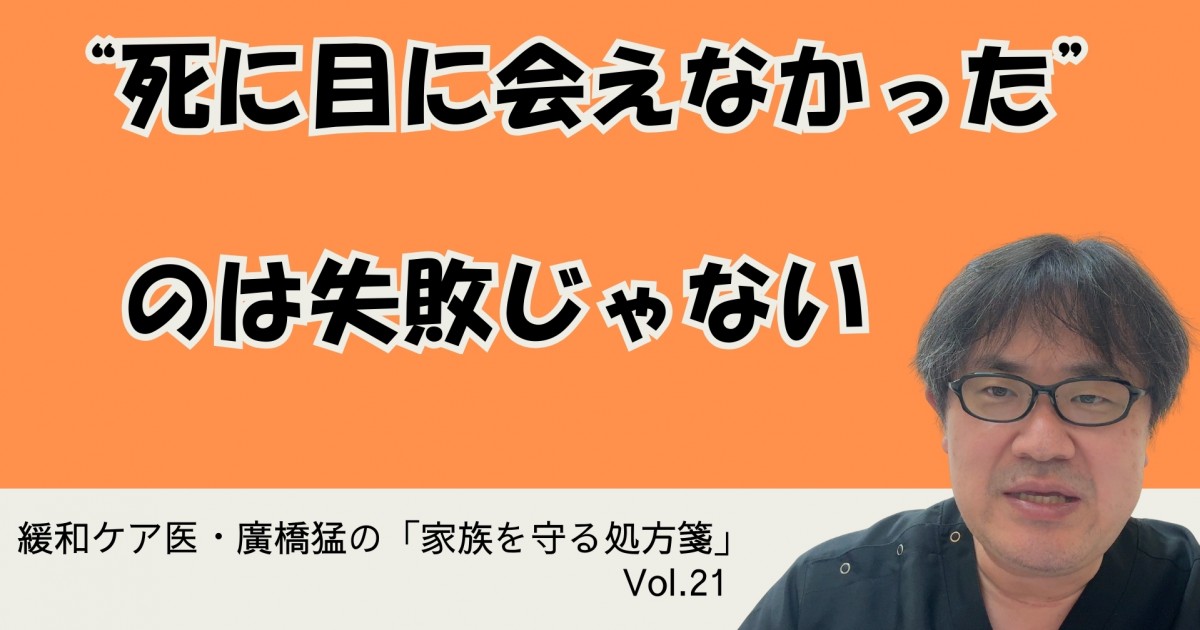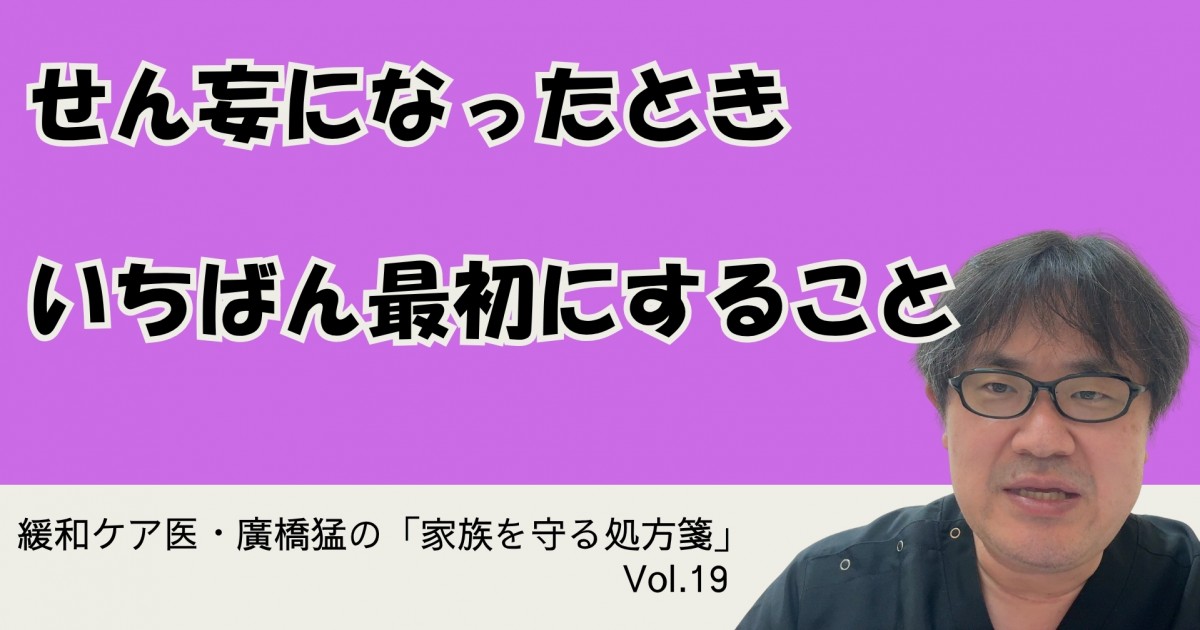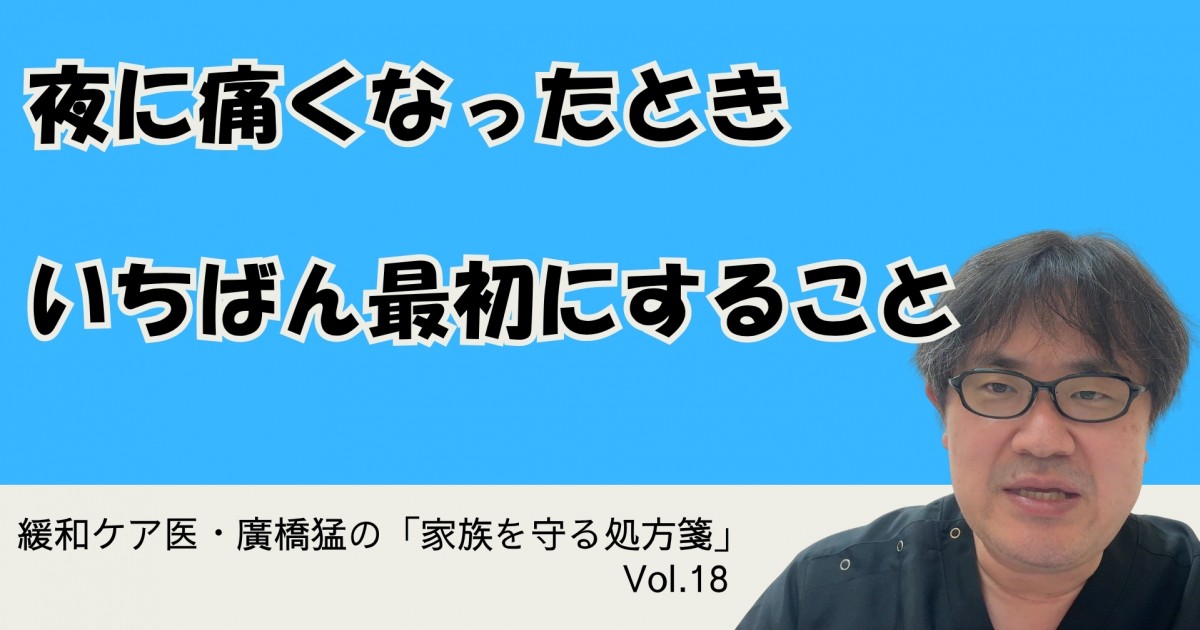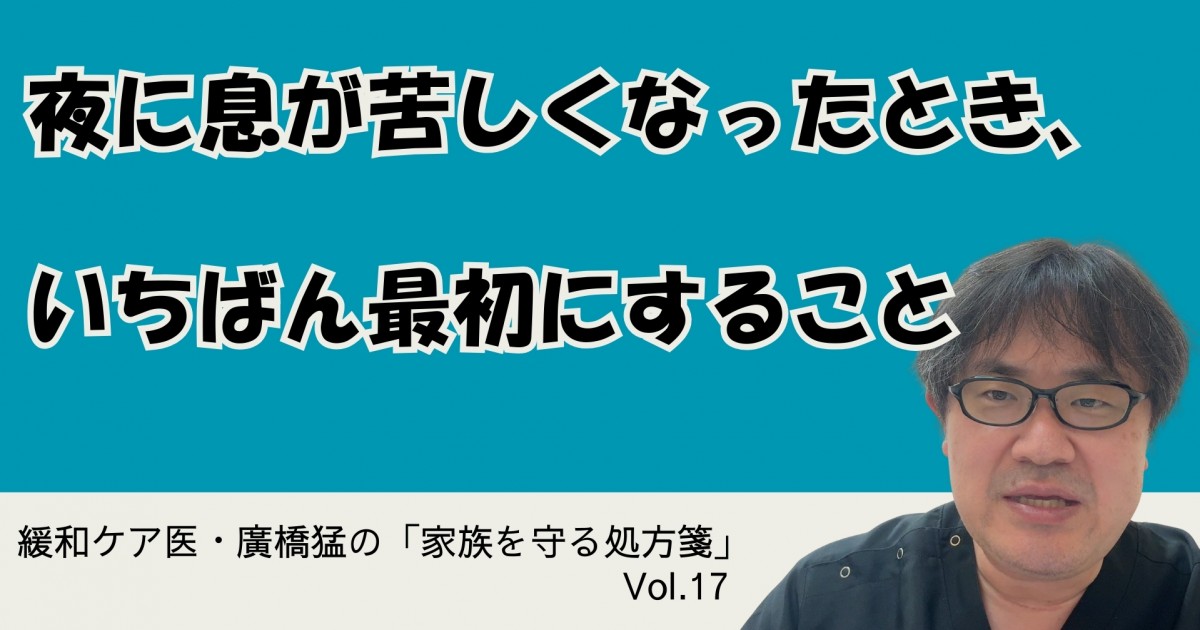マクドナルドが食べたい末期患者 〜自宅で起きた小さな奇跡と、緩和ケアの本質〜
皆さん、こんにちは。緩和ケア医の廣橋猛です。
このニュースレター「家族を守る処方箋」では、ご家族の看病や看取りに直面する皆さんが抱えている不安や悩みに対して、少しでも役立つヒントをお届けしています。
さて、本編に入る前に、読者の皆さまにお願いがあります。この度、読者さま向けアンケートを実施することになりました。本レターをより改善して、皆さまに役立つものにしていきたいと考えています。以下リンクから、何卒ご回答よろしくお願いいたします。回答は1分以内に終わるものです。
「もう、病院のご飯は食べられないよ」
特に人生の終わりが近づいてこられている患者さんのケアをしていると、私たちはしばしば「栄養」という大きなテーマに直面します。
体力を維持するために、バランスの取れた食事をどう提供するか。それは医療者にとって、またご家族にとっても、非常に重要な課題です。
しかし、本当に大切なことは、カロリーや栄養バランスの数字だけなのでしょうか。
今回お話しするのは、「食べる」という行為が持つ、栄養以上の深い意味について、私自身が深く考えさせられた、ある患者さんとの記憶です。その方は、病院の食事にほとんど手をつけず、たった一つ、意外なものを口にしたいと願っていました。
このお話が、いまご家族の看病や介護に奮闘されている皆さんにとって、大切な人との時間を見つめ直すための「処方箋」となれば幸いです。
1. 病院のベッドで生まれた、ささやかな願い 「俺はマックが食べたい」
季節が移り変わるある日の午後、私は担当する患者さんの病室を回っていました。
その中に、50代の男性、小林さんがいらっしゃいました。
小林さんは末期の肺がんで、呼吸の苦しさに加え、骨への転移による強い痛みがあり、入院での緩和ケアを受けていました。
幸い、モルヒネの持続的な注射によって、耐えがたい痛みや苦しみは落ち着いていましたが、彼の身体は病によってずいぶんと痩せ細り、病室の中を数歩、壁を伝って歩くのがやっとという状態でした。
私が訪れたのは、ちょうど昼食が運ばれてきたタイミング。しかし、お膳の上のお皿にはほとんど手がつけられていません。力なくベッドに腰掛けていた小林さんは、私に気づくと、少し苛立ったような、それでいて懇願するような目でこう言ったのです。
「先生、こんな病院のご飯じゃ、もう食べられないよ。俺は……俺はマックが食べたいんだ」

病院の食事は、管理栄養士の方々が栄養のバランスを考え、限られた予算の中で最大限の工夫を凝らして作ってくださっています。しかし、どうしても治療の影響で味覚が変わってしまったり、見た目や香りで食欲が湧かなかったりする患者さんにとっては、その「正しさ」が、かえってつらく感じられることがあります。
私は努めて穏やかに返しました。
「小林さん、気持ちは分かります。でも、病院の食事も身体のことを考えて作られているんですよ」
「そんなことは分かってる。分かってるけど、俺はマックじゃなきゃ、もう何も食べられないんだ」
彼のその言葉には、単なるわがままではない、切実な響きがありました。これまで彼は、病状が進む中でも治療に弱音を吐くことはほとんどありませんでした。そんな彼が、これほど強く何かを求める姿を初めて見たのです。
ご家族からの差し入れは特に制限していなかったので、私は次の提案をしました。
「でしたら、今度ご家族にお願いして、買ってきてもらいましょうか?」
すると、小林さんは寂しそうに首を振りました。
「持ってきてもらう頃には冷めてるだろ? それに、この無機質な病室で一人で食べたって、味気ないじゃないか」
その言葉に、私はハッとさせられました。彼が求めているのは、マクドナルドという「食べ物」そのものだけではないのかもしれない。その先にある「体験」や「時間」を欲しているのではないか、と。