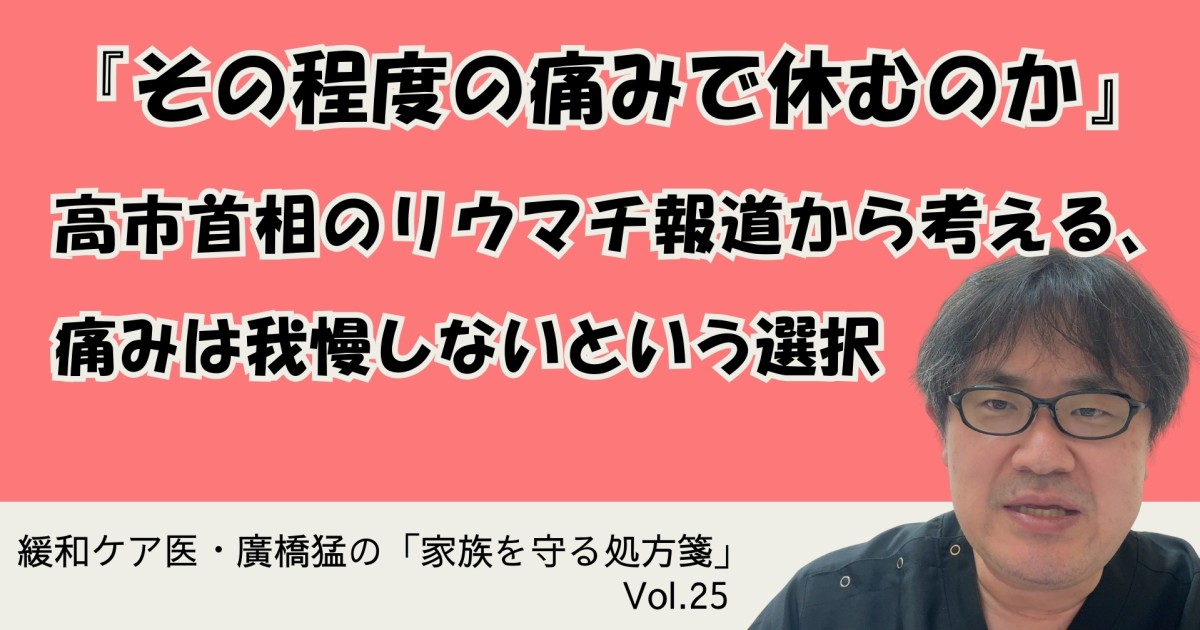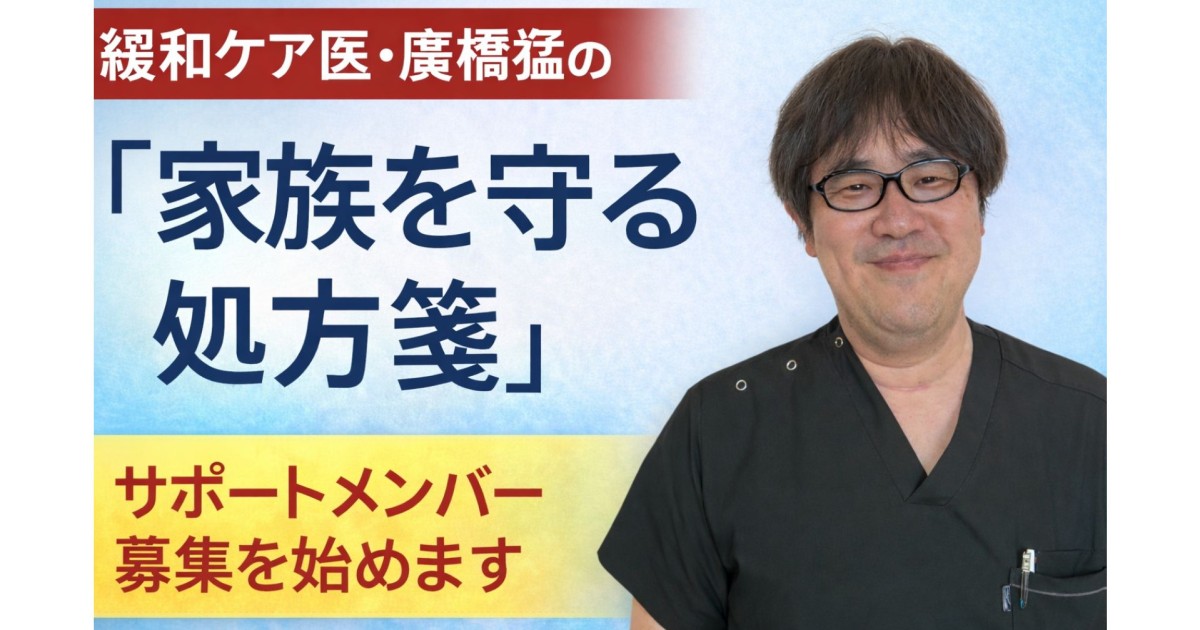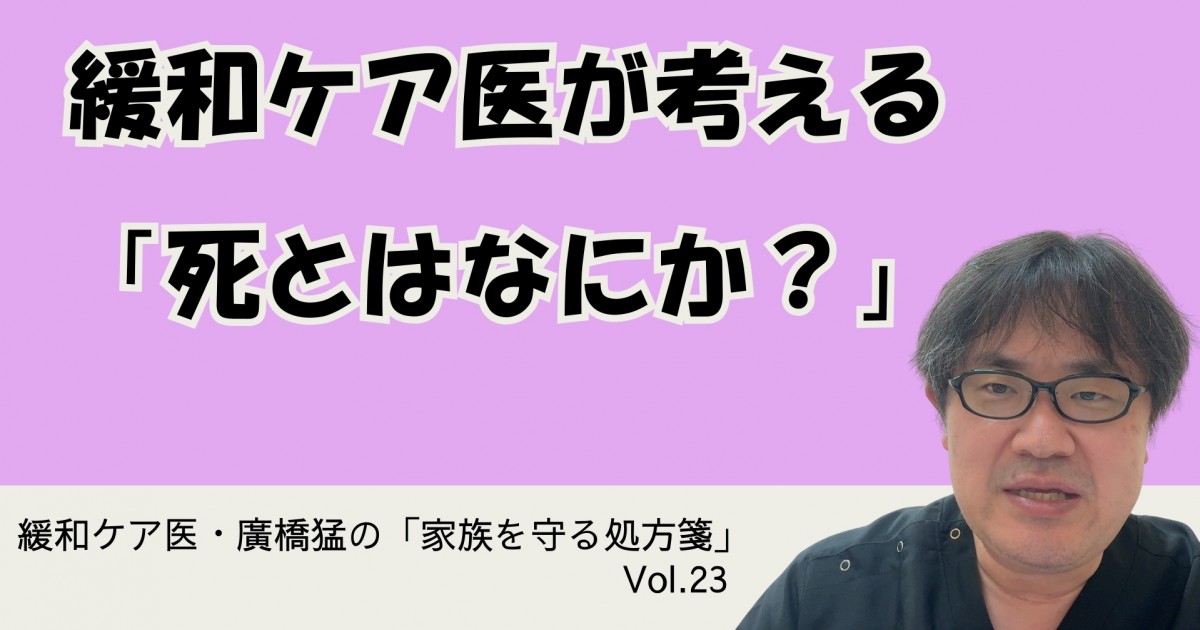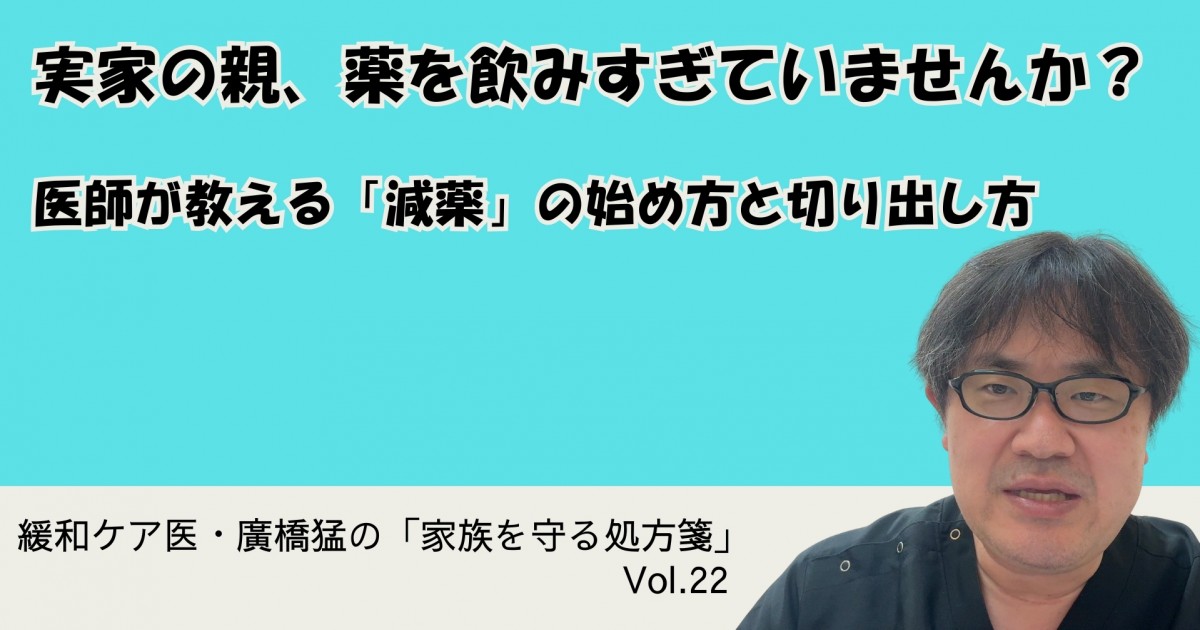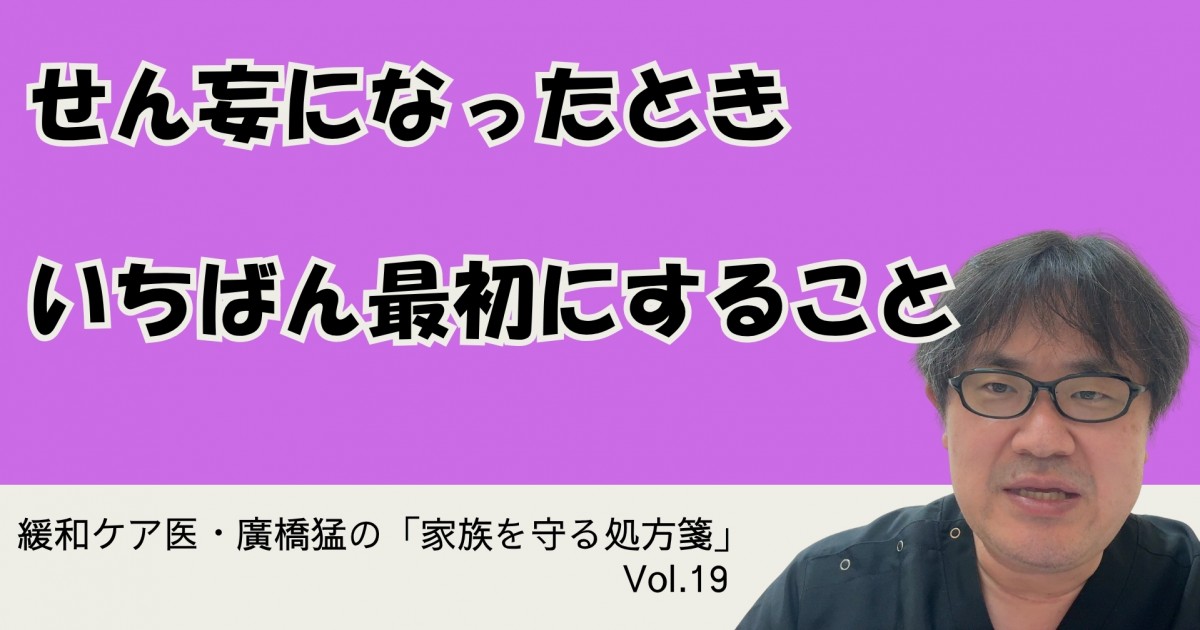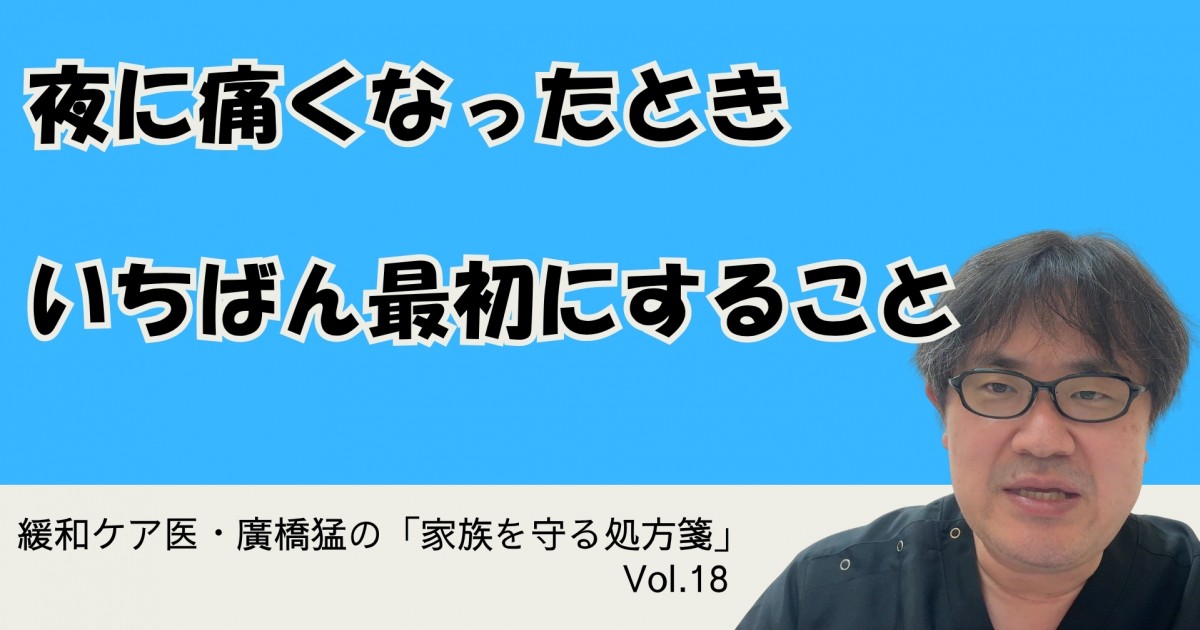“死に目に会えなかった”のは失敗じゃない
「間に合わなかった娘」─それでも母は“最後の日常”を娘と過ごしていた
「先生……最期に間に合いませんでした」
理沙さん(40代)は、診察室に入ると同時にそうつぶやきました。目元は赤く、眠れなかった夜の痕跡がそのまま残っていました。
お母さまは胆管がんの末期で、自宅での療養が困難になり入院されていました。
一人娘である理沙さんは、この数週間、ほぼ毎日病院に通っていました。仕事を終えたあと病室に向かい、椅子を並べて母とおしゃべりをする。他愛もないことを話す、ごく普通の時間。
「今日スーパーでおいしそうなパン見つけたよ」
「そのハンドクリーム、いい匂いね」
「明日も来るからね」
お母さまの身体は日々弱っていきましたが、それでも亡くなる前日も、まったく同じ時間が流れていました。
理沙さんにハンドクリームを塗ってもらったお母さまは、「気持ちいいねぇ」と目を閉じ、嬉しそうに手を預けていました。それを見て理沙さんは笑いながら、「また明日ね」と病室を出たのです。
その“何気ない日常”こそが、お母さまの安心そのものでした。
しかし……その夜、深夜2時。
理沙さんが帰った後、お母さまは眠るように穏やかに息を引き取りました。
急変に気づいた看護師は、急いで理沙さんを呼んだのです。

翌朝、私は理沙さんと診察室でお話しました。
「一人にしてしまったんじゃないかと思うと……」
理沙さんの声は震えていました。
私はゆっくりと伝えました。
「理沙さん。お母さまは前の日、とても安心していましたね。手をさすってもらったときに、『気持ちいいね』って。“あの時間”が、お母さまにとっての看取りの時間でもあったんです」
その瞬間、理沙さんの肩がふるりと震え、堪えていた涙が一気にあふれました。
「…あれが、母との“最後の会話”だったんです。あんな普通の時間でよかったんでしょうか」
はい。大切なのは、最期の瞬間の“立ち会い”ではありません。
その人が安心して過ごせた時間、その積み重ねこそが、看取りなのです。
この出来事は、私がずっと伝えたいと思っていた誤解に改めて向き合うきっかけになりました。
多くのご家族が、「死に目に会えなかったら失敗」と思い込んでしまう。でも、それは本当に正しいのでしょうか?